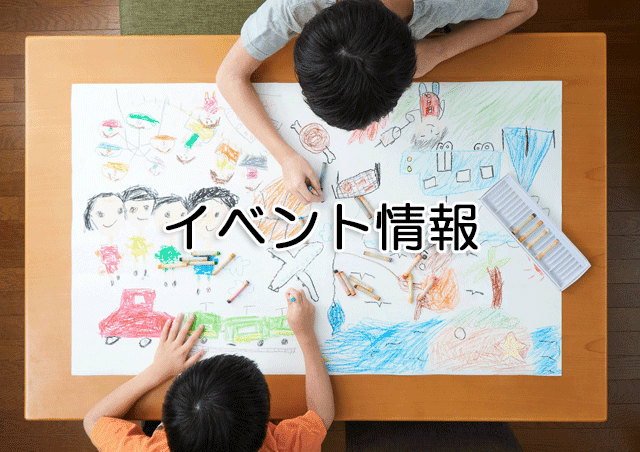【2025年1月29日(水)】
こんにちは!平久小学校地域学校協働本部です。
絵画を鑑賞しながら色々なお話を楽しむ放課後ワークショップ「みるはなきっず」第7回がスタートしました!

冬の寒さを一段と感じる1月末。
旧暦の新年にちなんで真冬の街角、風物詩を描いた西洋画と日本画を題材に「みるはなきっず(対話型鑑賞)」を行いました。
放課後に集まったのは1年生から3年生の13人のこどもたち。
荷物を置くと早速モニター前の席に向かい、筆記用具など準備を整えるのもお手のもの。
早く絵を見たい、話したい気持ちがあふれていました。
そこで今日は少し落ち着くために一度、目を閉じて、目と耳の感覚を澄ますところから始めてみました。
こどもたちは自分の意見を発表する、質問に答えながらさらに自分の考えを話す、お友達の意見から視点をふくらますなど、本当に得意になったと感じます。
もちろん、ずっと聞いている子もいますし、承認欲求の塊のようなお年頃ですから目立ちたい、笑いを取りたい心理で賑やかなのも可愛いものです。
どんな参加姿勢でも多様な意見を受け入れて新しい視点を発見していくことを楽しんでいるのが分かります。
終了後は、すっきりしたような、達成感のある表情も印象的です。
みるはなきっず以外の時間でも「よく見る、考える」ことが習慣になって来ているのではないでしょうか。
みるはなきっずでは、鑑賞した作品を後から振り返られるように絵のプリントをお渡ししております。
今まで、自主学習のテーマにする場合に調べやすいように、絵の題名、作者、制作年、所蔵先を記載していましたが、今回それをやめて絵だけにしたところ、早速こどもたちから「題名が書いてなーい!」と不満気な指摘がありました。
「みんな自分なりの見方ができたから、題名は知らなくてもいいよ」と伝えたのですが、納得がいかないようでしたので黒板に書くと、慣れない漢字も含めて一生懸命に書き写している子がたくさんいました。
対話型鑑賞では作者や題名と言った情報は一旦置いておき、まずは自分の目で見て考えたことを尊重するので作者や題名を伏せたまま対話を終えることも珍しくありません。
また、誰もが知識に頼らず新鮮な視点で鑑賞できるように、あまり有名ではない絵を選定することも多いです。
みるはなきっずでも安易に「これ知ってる!」とならないような、こどもたちが興味を持ちそうなポイントが多い絵を選び、知識偏重にならないように配慮しております。
こどもたちが安心して、知らない、分からなさの中にあるおもしろさを体験できるよう、みるはなきっずは、こどもたちの成長と楽しい!を軸にさらに工夫を重ねて参ります。
(文章)みるはなきっずファシリテーター:みゅうゆう
みゅうゆう先生&りお先生
【対話型鑑賞について】 NY近代美術館が開発したプログラムで、絵を見て自分が感じたままを話し、他人の意見を聴くことで観察力、思考力を深め、対話によって共感力、想像力、自己肯定感が高まる効果が期待できるというものです。 対話型鑑賞で得られる効果はハーバード大学によって実証されており、近年では大学から小学校、幼稚園、企業などが取り入れています。 |