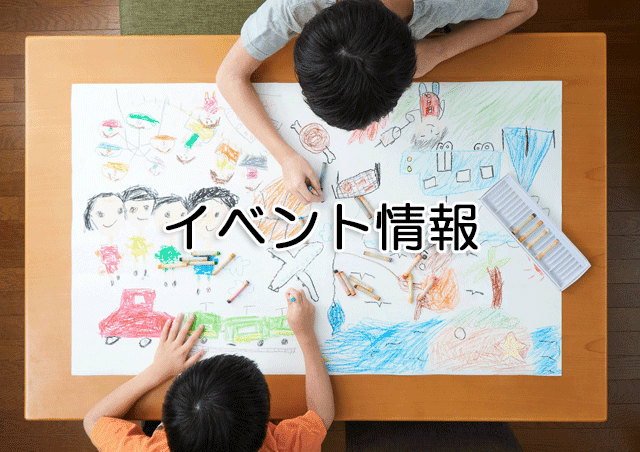【2025年9月20日(土)】
こんにちは!平久小学校地域学校協働本部です。
絵画を鑑賞しながら色々なお話を楽しむワークショップ「みるはなきっず」を9月ウィークエンドスクールとして開催しました。

今年度はじめての親子みるはなきっず。
3枚の絵を鑑賞した後に机4つ分の大きな紙に絵を描くワークまでの、ストーリー展開を含む90分プログラムでした。
対話の1枚目、皆さん集中して身を乗り出したり、モニターの近づいて観察。
先生の問いかけに、人々の様子や建物、遠景、時間に注目した発表があり
「とまっている船と帰ってくる船がいるから夜だと思う」から
「暗いから、細い月か、月が出ない夜のお祭りで人が集まっている」と、
描かれていない月へ想像が広がりました。

続いて2枚目、先ほどと同じ日本画ですがかなり具体的な絵。
大人から「潮干狩り」と早速の発言に続き、潮の満ち引き、浜辺と海の様子、人々の様子、天気、時間と展開し、「これは◯◯図書館」「太陽光パネルもある」と、昔の絵に今と未来も描かれていることにワクワクな想像が止まりませんでした。
そして「ここに月がある」との大発見!上の方の真ん中の美しい青の中に小さい月が出ていたのです。
なんと、3枚の絵は月でつながりました。
休憩の後は、先ほどの潮干狩りの絵が実は平久小学校あたりの絵という種明かしとなる
江戸時代と現在の地図が移り変わる動画を見て、一同びっくり!
これ以上の説明は江戸の人に野暮と言われそうなので、この先は皆さんの想像におまかせします。

そして、江戸時代に想いを馳せながら2グループに別れて大きな絵をみんなで協力して描きました。
自分の描きたいもの、つられて描きたくなったもの、相談しながらどんどん思いついて手を動かしました。
いつの間にか大人も本気モードでしたよ。
あっという間の90分、絵を見てお話しするところからスタートして
対話が進むうちにお互いを知り、頭もフル回転、年齢差に関係なく夢中になる楽しい時間となりました。
ひとりで見ても思いつかないような発見にあふれて、大人は思い込みの枠を外して、
改めてみんな見る面白さの再発見でした。

さて、今年の十五夜はこれからです。
夜空の月を見ながら江戸時代に想いを馳せるのも素敵ですね。
そして偶然ですが、中川船番所の特別展「江戸の出版文化と江東地域」で今回の絵の本物が展示されています。
どうぞ皆さんも見に行って本物の絵から発見してみてください。
みるはなきっずファシリテーター:みゅうゆう
(対話型鑑賞アートマインドコーチングアドバンスコーチ
【対話型鑑賞について】 NY近代美術館が開発したプログラムで、絵を見て自分が感じたままを話し、他人の意見を聴くことで観察力、思考力を深め、対話によって共感力、想像力、自己肯定感が高まる効果が期待できるというものです。 対話型鑑賞で得られる効果はハーバード大学によって実証されており、近年では大学から小学校、幼稚園、企業などが取り入れています。 |